
知育っていつからはじめたらいいの?
うちの子はもう遅いんじゃないかな。

知育を始める時期って迷いますよね。
私も3人の子どもたちを育てる中で、知育をいつからするのか、
うちの子たちはもう4歳、5歳だし遅いんじゃないのか…
そう悩んだことがあります。
でも、大丈夫!
知育に関心を持った“今”が、あなたにとって、
そしてお子さんにとってのベストタイミング。
この記事を読めば、知育を始める時期への不安が解消され、
今日からおうちで無理なくできる方法が見つかります。
知育は、特別なことでも、難しいことでもありません。
わが子の成長を優しく見守り、応援する、ごく自然な関わりのことです。
知育への不安を少しでも解消し一緒に知育の第一歩を踏み出してみませんか?
「早く始めなきゃ」は思い込み?知育に“正解の時期”はありません

知育は0歳のうちにはじめないと手遅れ?!
SNSや周りのママを見ると始めてるママが多い…
こんな風に焦ることありますよね。
私も長女の初めての子育ての時は周りを見てはすごく焦っていました。
でも、結論
確かに、周りのママが知育を始めてこんな効果があった!
なんて聞くとうちも早く始めたほうがよかったんじゃないかな…
って心がザワザワすると思います。
でも、それはそのお子さんにとってちょうどいいタイミングだっただけ。
大切なのは我が子とママ自身のペースに合っていること
それに焦ってしまうといいことは何もありません。
- 周りと比べてしまい不安が大きくなってしまう
- 知育を義務に感じてしまう
- 子どもとの気持ちが合わず、イライラしてしまう
そんな風に子どもにとってもママにとっても焦って始めてしまうことは
マイナスな側面が多いです。
だらこそ、やってみたいと思ったその時がベストタイミング!
でも、正直気になりますよね…
実際、みんなはいつから知育を始めてるの?
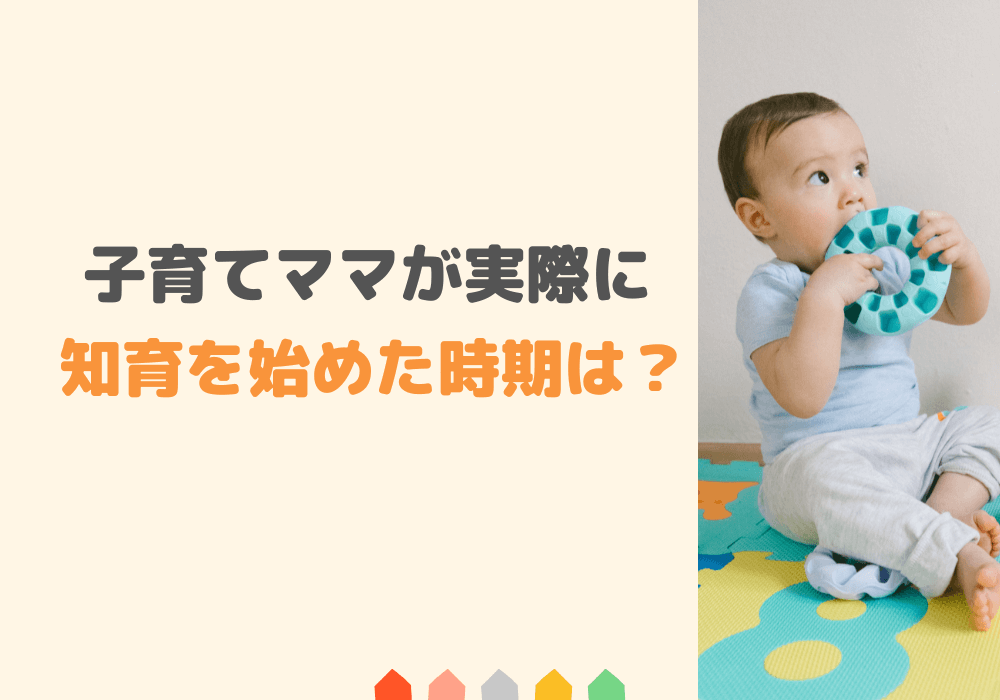
2021年に行われたninaruポッケのアンケートによると
0歳で知育を始めた家庭が7割。
また、興味はあるけどまだ始めたことがない人も7割の人は
1〜3歳の間に始めたいと思ってるとの回答
この結果を見て
やっぱりみんな早い時期から始めてる…
うちはもう3歳過ぎてるし…
とちょっと焦ってしまう気持ち、すごくよくわかります。
実は私も知育について知り、学び始めたのは3きょうだいの末っ子が0歳の時。

上2人の子どもたちは年子で大変だったから…
と自分に言い訳をしていたくらいです(笑)
でも、視点を変えてみると
1週間の生活を振り返ってみた時
- 寝る前の絵本の時間
- 夕飯作りのお手伝い
- 園からの帰り道のお散歩
- 休日の公園での虫取り
全てが知育に繋がっています。
普段の生活や子どもたちとの何気ない関わりで気づいたら知育を始めていた
なんてママも多いのではないでしょうか?
そう思うと
「いつ始めるか?」より「どう関わるのか」の方が大切
だと感じませんか?
子どもたちは親の表情や行動をしっかり見て、感情さえも汲み取ってる。
だからこそ、ママやパパの「我が子とどう関わりたいのか。」の方が
ずっと大事になってくるんです。
普段の生活が知育につながっていると言うことは
特別な教材や知識がなくとも「すでに知育は始まっている」
と言うことになります
ママやパパが「どうして?」「なんでだろう?」と会話することで
知育の土台はすでに作られているんです。
忙しい中でママやパパが関わってくれていることは
知育の種まきになっています。
そしてその種をちょっと意識して水やりしてあげることで
- 「得意」がもっと伸びる
- 「やってみたい!」の気持ちが育まれる
- 我が子の「好き」が見つかる
といった子どもたちの変化があり、子どもたちの世界もぐんと広がります。
うちはもう遅いかも…
そんなことはありません。
ママやパパが「知育をやってみたいな。」「気になるかも!」
そう思った今こそが知育を始めるベストタイミングなんです。
知育を始めるベストタイミング=親子で楽しめる今

知育を始めるなら
「しっかりと準備をしてからはじめたい!」
「やるならしっかりと教えたい。」
そう思って、なかなか一歩が踏み出せないママもいるでしょう。
でも、実は知育の中身よりも
「楽しい」が1番の知育なんです
子どもたちにとって「楽しくてワクワクする気持ち」は
学びのスイッチをオンにしてくれるもの。
だから、ママが「やってみようかな!」
そう思った時が始めどきなんですが
「せっかく始めたのに続けられなかったらどうしよう…」
「忙しいのに毎日、時間なんて作ってあげられない。」
そんな風に思うことありますよね。
私も3人の子育てをしていて、子どもたちそれぞれと
ゆっくり向き合う時間を持ちたいとは思っているものの
実現できないことが多々ありあます。
でも、大丈夫!
無理のない範囲でできることがたくさんあります。
例えば
- 絵本を読むときに少しだけ問いかけを増やしてみる
- 夕飯に出てきた食材について形や色を観察してみる
- 子どもが遊んでいる時に「何をするの?」「どんなもの作るの?」と聞いて想像を広げる
こんな風に日常生活の何気ない場面から知育の要素に広げられることができます。
忙しくてもできる!【おうちで簡単知育】アイディア5選

「よし、やってみよう!」と思っても
何からしたらいいかわからない…
なんてことありますよね。
特別な教材や環境がなくても、子どもと今過ごしている「おうち時間」が
最高の知育タイムになる方法をお伝していきます!
我が家でも実践していて、子どもたちの反応もその時々で変わるので
毎日やりがいがあります。
絵本タイムにプラスの『問いかけ』
絵本を読むことに加えて
- 「この後、どうなると思う?」
- 「どのキャラクターが好き?」
- 「この動物の名前はなんだろう?」
と質問していくことで、想像力や表現力を育むことができます。
お手伝いの時間をフル活用
料理や洗濯などのお手伝いの中でも知育の要素はたくさんあります。
例えば
- 野菜の色や形、触り心地について観察してみる
- どんな順番で掃除していくか一緒に考える
- 野菜をちぎったり、卵を混ぜたり、料理の盛り付けをする
- 洗濯物をハンガーにかけて干す
これらのことから、観察力、思考力、手指の巧緻性が育まれます。
お散歩、外遊びは発見の宝庫
お散歩や公園で過ごす時間は季節を肌で感じることができ、知育の宝庫と言えます。
また、自然にいる虫や動物を観察することも知育の時間となります。
五感をフルに使うので五感がより一層育まれ、観察力も養うことができます。

お外遊びに付き合うってママにとっては気力も体力も必要。
子どもたちはアリの観察を何十分もしていたりなんてよくあります。
なので、お散歩や外遊びはママの気持ちに余裕があって
時間にも余裕がある時がオススメ!
おしゃべりを考える時間に!
普段、何気なくしている会話の中に
- 「〇〇ちゃん、〇〇くんはどう思う?」
- 「ママはこう思うんだけど、どうかな?」
- 「それはなんでだと思う?」
といった声かけを入れることで、表現力、思考力、共感力が育まれます。

「はい」「いいえ」で答えられるイエス・ノーの質問よりも、
「何が楽しかった?」「どう思った?」といったオープンクエスチョンを使うと
子どもが自分の気持ちや考えを言葉にしやすくなります。
会話が広がり、親子のコミュニケーションもより深まるからオススメです。
ごっこ遊びは無限大に遊びを広げられる
ごっこ遊びでは役になりきったり、どんなごっこ遊びをするのか
自由に考える場面がたくさんあります。
ごっこ遊びを通して、想像力、思考力、構成力が育まれます。

我が家では「お片付け屋さんごっこ」を称して、最近では
お片づけの中にごっこ遊びをと取り入れています。
これが子どもたちには大好評で片付けの時間が半分になりました!
まとめ
知育をいつから始めたらいいんだろう?
そう悩むママも多いですが、大切なのは
“いつから”ではなく”どう関わるのか”
日常の中での声かけや生活に知育の要素がたくさん!
何気なく話していたこと、何気なくやっていた行動が実は知育に繋がっています。
子育てをしていると思い通りにならないことばかりです。
だからこそ、知育を『頑張るもの』ではなく『楽しむもの』にしてほしいと
私は思っています。
ママやパパの笑顔が子どもたちにとっての知育の土台。
親子で楽しむ時間をより濃いものにしていきましょう!
今の我が子にあった知育を始められるようにまずはそれぞれの年齢にあった
知育方法を学んでみてくださいね。
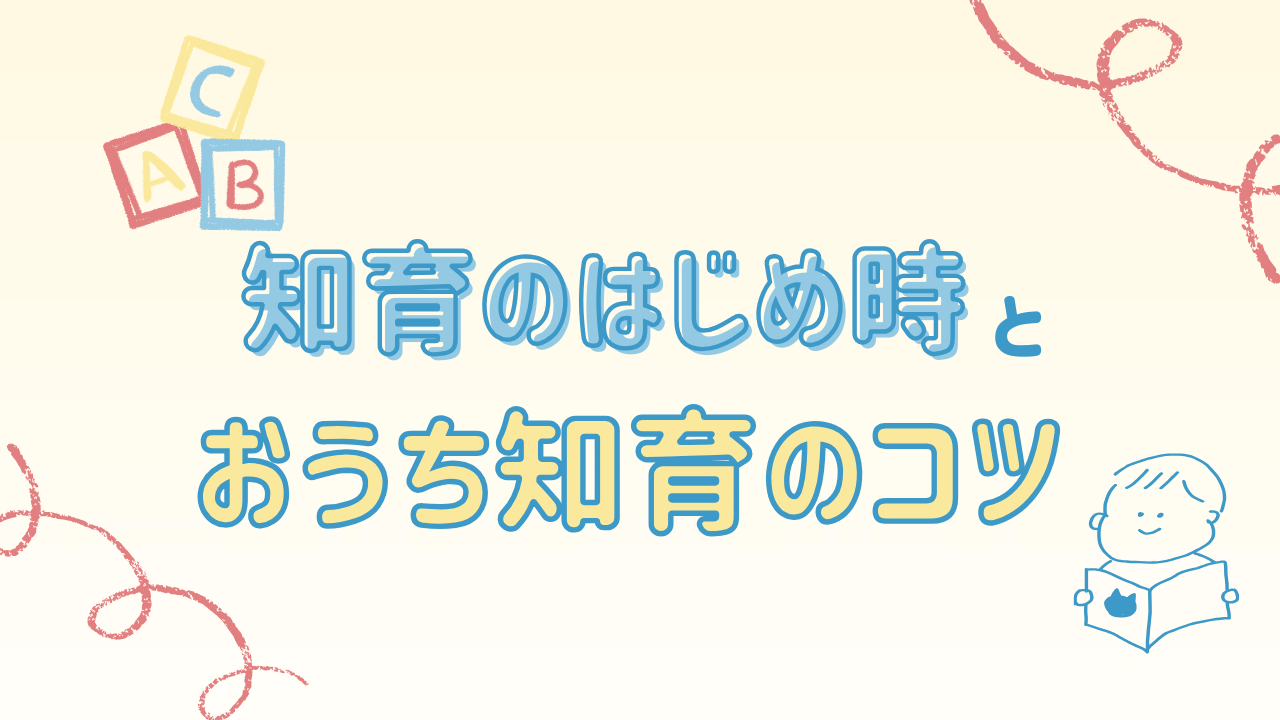
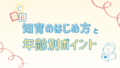
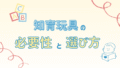
コメント